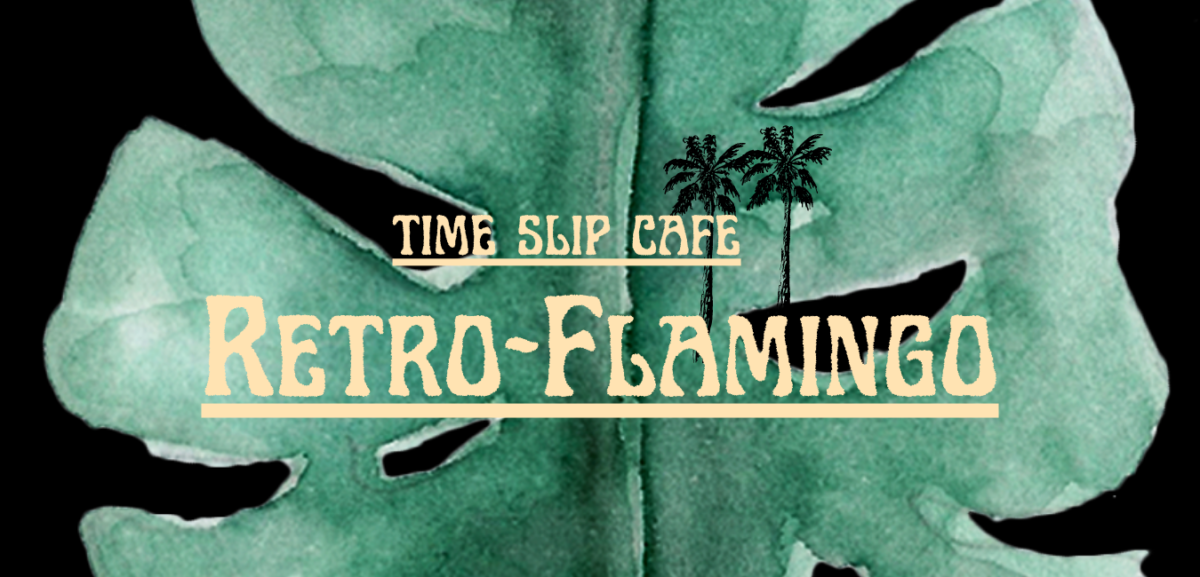スポンサーリンク
こんにちは‼
retro flamingoへようこそ‼
本日も宜しくお願い致します。
『京都』
誰しも憧れる観光地…嵐山辺りに行きますと人力車に乗って颯爽と見物されておられますね〜 まじかで見ると浪漫チックでとても絵になる光景です。 私は残念ながらまだ乗ったことはないのですが…
人力車を見て 浮かぶのは、私が子供の頃にテレビで放映されていた、大正時代の世相を描いた漫画 はいからさんが通る(大和和紀さん ・漫画家)
明治〜大正時代 沢山の洋風文化が急速に浸透し日本文化に西洋文化が積極的に取り入れられた大正ロマンが背景でした。
現在も様々な観光地で体験出来る人力車ですが、主に明治〜大正・昭和初期にかけ移動手段として用いられていました。『人力俥 』とも表記するそうです こちらの方がなんだかカッコイイですね〜
ですが 、やがて馬車 鉄道 自動車が普及し都市圏で1926年頃、地方でも1935年頃をピークに減少し 現在では一般的な交通・運送手段としては使用されなくなりました。
しかし昭和初期までは一般的に存在した庶民的な車両であるため、各地の博物館や資料館などにも保存 展示されています。
観光では1970年飛騨高山のごくらく舎で最初に用いられ、テレビ番組の紹介などにより、京都といった風雅な街並みの観光地から〜浅草などの下町・伊豆伊東、道後といった温泉町や大正レトロの門司港と有名観光地に広がっていったのでした。
その人力俥なのですが、発明をめぐり幾多の説が上がり発明人に対する議論が行われ、結果…記録上では日本の和泉要助、高山幸助、鈴木徳次郎の3名が発明者として明治政府から認定されたのでした、しかしその効力たるものは数年で有名無実となり、そこから急速な普及により1876年には東京府内で2万5038台、19世紀末の日本には20万台を越す人力俥があったとのことで、当時の人々の生活の足だったのがうかがえます。
そしてアジア各地に輸出され東南アジアの多くの都市でも見られるようになりました…
私たちの日々の生活において とても重要な移動手段となる乗り物は、先人の多様な発明と開発の積み重ねにより今にいたりますが、
今回の人力俥は大正ロマンと言う時代の代名詞となって私たちに 美しい当時さながらの画角を見せてくれるのです‼
今度一度乗って見ましょう…私も…
今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました。
又 お待ちいたしております。
retro flamingoでした‼
関連記事『文明開化』服装の変遷

メッセージが送信されました
スポンサーリンク