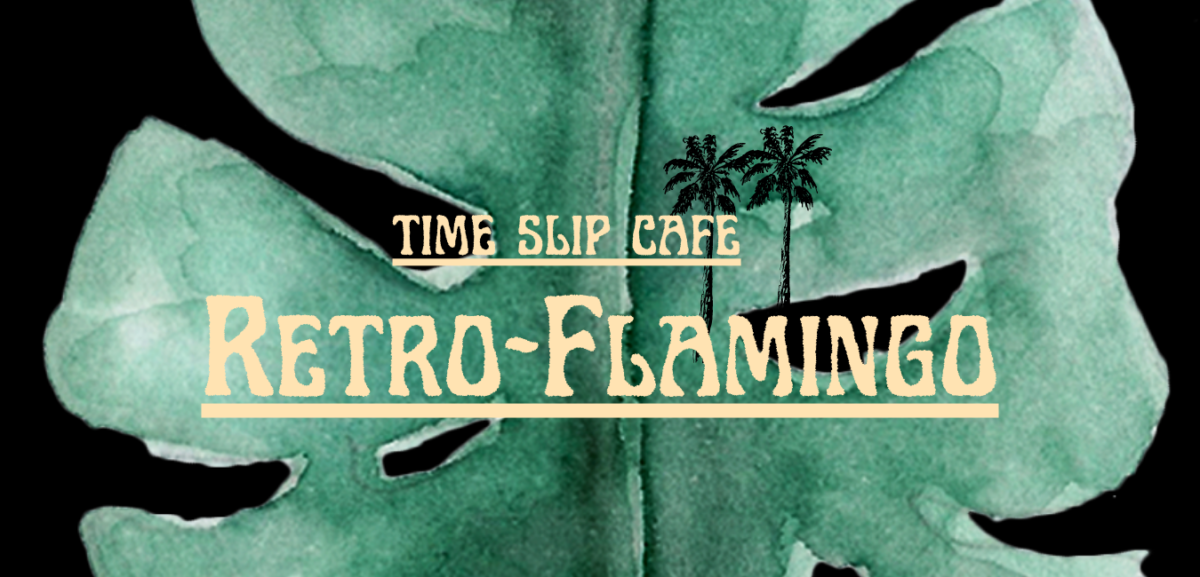スポンサーリンク
こんにちは
過去を考察する
ブログ
retro-flamingoです。
今回は レトロ感をまとうフォルムの
ボンネットバス(ボンバス)をピックして
奮闘していた時代にフォーカスしていきます。
ボンネットバスご存知ですか❓
各地の観光地では懐かしの名物として今でもボンネットバスを利用しているところもあり、
昭和のレトロ感あるシートに座り車窓から眺める景色は格別でしょうね。
それで今回の
初めのテーマにある「omnibus」(オムニバス)
について進んでいきましょう!
バスと呼ばれる由来に因みます。
{オムニバスがバスの語源}
ラテン語のomnibus(オムニブス)は「全ての人のために」
と言う意味で…
フランスの実業家
スタニスラス・ボードリーが乗合馬車事業を始めたころ
フランスの西部、ロワール川河畔の都市 ナント(Nantes)中心部のコメルス広場にあったomneという帽子屋の前に
「OMNES Omnibus」という看板をかかげていました。
この看板が馬車乗り場の目印となり、やがてオムニビュスと呼ばれるように、
そして…
omnibus〜busと短縮され今のバスに定着しました。
「全ての人のために」から発生した語源は公共の交通機関として活躍するバスの意義を表すものであるのですね、
『ボンネットバス』(ボンバス)
前部に突出したエンジンルームを持つ(ボンネット)形状は衝突の際は緩衝作用を担い安全性を付加し
騒音・振動も静で客室の安静化に効果のある構造で
現代でも見られるアメリカの大型トラックがそれである。

1950年代頃
街にはボンネットバスが行き交い、人々に「鼻高バス」の愛称で呼ばれ利用されました。
時の世相は 伝統・習慣・制度・社会組織・考え方などを尊重する保守的な傾向にあり、
それによる対抗文化から若者文化が生まれた時代でした。
歌声喫茶やうたごえ運動と言った文化運動や
若者文化を示す「太陽族」が流行します。
石原慎太郎の小説『太陽の季節』に因む文化は
享楽的な若者を示すもので、
サングラス、アロハシャツの不良集団でした。
出で立ちから得意文化が生まれるのは常ですね、
この様な若者文化の明確な定着には時代背景に通信や交通網の発達が挙げられます。
交通網の活性化により、旅をする手段も容易になり若者の文化の拡大また情報の伝達もこれまでより広範に伝わる事になりました。
日常のみじかな移動にはボンネットバスは俗識であったでしょう、
今もそうでありますが、当時は自家用車などをまだ持たない頃を表現するものであります。
この頃から1960年代まではバスにも「車掌」が同乗していました、
大正〜昭和初期には「バスガール」が同乗するのが当たり前で、
当時にはモダンな制服を採用し女性の憧れの職業となり、
当時では女性の社会進出の先駆けと言える仕事でありました。
見知らぬ土地(環境)へ夢をはせ行動出来る
社会における若者のバイタリティーを感じます。
そんな共有する社会に
『omnibus』(全ての人のために)から始まり活躍した
『ボンネットバス』は今も存在しその車窓から当時の原風景を想い起こさせてくれ、
近代日本史を体感させてくれるのです…
いつの日か『ボンバス』に乗り巡って見たいものです。

今回はこれでおしまいです。
retro-flamingoでした。
メッセージが送信されました
スポンサーリンク