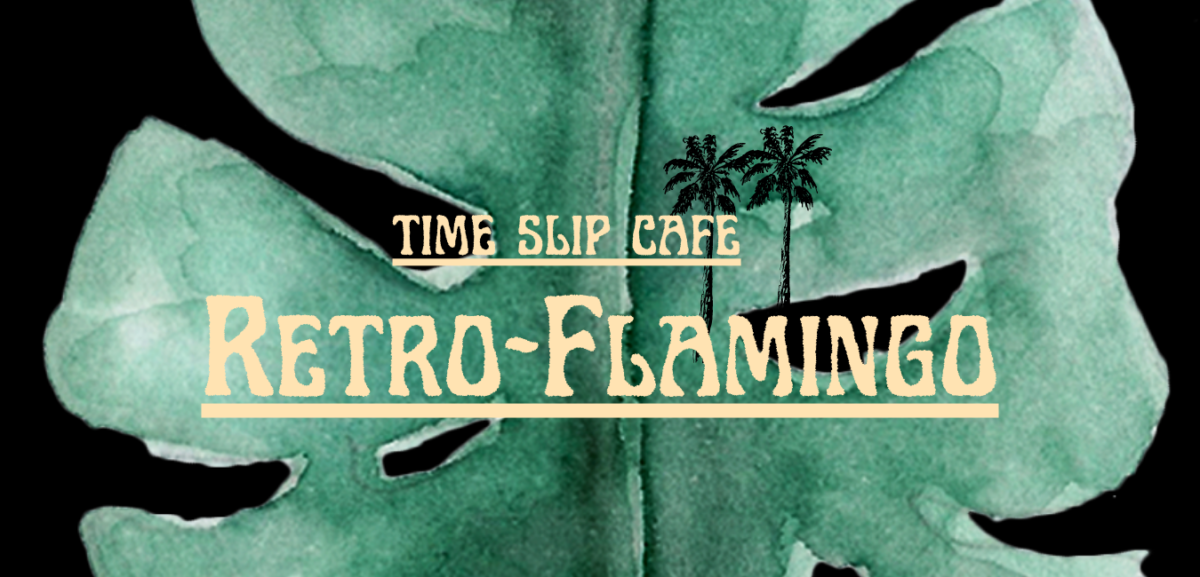冷蔵庫を開けると、高確率でドアポケットに鎮座している赤いボトル。そう、トマトケチャップ。ポテトフライにかけたり、オムライスにかけたり、私たちの食卓に欠かせない定番調味料。
でも、ちょっと待ってください。
この赤いソース、もともとは”魚臭い醤油”だったって知っていますか?
「ケチャップ」という言葉のルーツは、なんと中国語の「鮭汁(kê-chiap)」にさかのぼります。そう、あの甘酸っぱい赤いソースは、500年以上前の中国沿岸部で生まれた魚の発酵調味料から始まったのです。
この記事では、「ケチャップ=トマト」という常識がひっくり返る歴史ツアーへご案内します。冷蔵庫の赤いアイツの正体を、一緒に探ってみましょう!!
第1章:中国・東南アジアの”元祖ケチャップ”は魚醤だった
物語の舞台は、500年以上前の中国沿岸部、福建省あたりから始まります。
当時、この地域では魚を塩と一緒に発酵させて作る、濃い茶色の液体調味料が重宝されていました。いわゆる「魚醤(ぎょしょう)」です。ベトナムのヌクマム、タイのナンプラーと言えば、ピンとくる方も多いでしょう。これらは全て魚醤の親戚なんです。
王信(ワンシン) 王信魚醤 300ml Amazon おすすめ 過去1か月で50点以上購入されました
福建語で「kê-chiap(鮭汁)」と呼ばれるこのソースは、塩漬け発酵魚から作った、強烈にうま味の濃い調味料でした。福建や東南アジアの港町では、中国人航海者や商人たちがこの魚醤を愛用し、船に積み込んで長い航海に出ていました。
想像してみてください。薄暗い屋台のテーブルに置かれた、褐色の液体が入った一瓶。蓋を開けると、鼻をつく魚の香りが立ち上る。
現代の私たちが知っているケチャップとは、まったく別物です。
ケチャップの原型は、屋台のテーブルに置かれた”強烈に魚くさい一瓶”だったかもしれない—そう考えると、なんだか面白くないですか?
この魚醤が、やがて世界中を旅することになるとは、当時の福建の人々も夢にも思わなかったでしょう。
第2章:ケチャップ、海を渡る ― ヨーロッパで”なんちゃって再現”が始まる
17世紀から18世紀にかけて、イギリスやオランダの船乗りや商人たちが東南アジアに進出しました。そこで彼らが出会ったのが、例の魚醤ソースです。
「このうま味、すごいな。ヨーロッパに持ち帰りたい!」
しかし、問題がありました。ヨーロッパには同じタイプの魚醤がなかったのです。そこで彼らは考えました。「ないなら、作ればいいじゃないか」と。
こうして始まったのが、“ケチャップもどき”の再現プロジェクトです。きのこ、クルミ、アンチョビ、牡蠣—手に入る素材で、あの濃厚なうま味を再現しようと試行錯誤が繰り返されました。
デルフィーノ コラトゥーラ・ディ・アリーチ(Dorica) 伝統製法で作られたイタリアの魚醤 250ml 【料理王国100選2019】 (単品)
18世紀のイギリスの料理書には、すでに
「mushroom ketchup(マッシュルームケチャップ)」などのレシピが登場しています。これは今の甘いケチャップとは正反対で、しょっぱくて旨味の強いドロッとした「ダシ醤油」のような存在でした。
面白いことに、あの『高慢と偏見』の著者ジェーン・オースティンも、マッシュルームケチャップを好んでいたと言われています。文学少女が愛したケチャップは、茶色でキノコ味—なんとも意外なギャップですよね。
ヨーロッパのケチャップは、もはや魚醤ではありませんでした。でも「濃厚なうま味調味料」という魂は、しっかり受け継がれていたのです。

第3章:トマト、ようやく登場 ― 19世紀アメリカの大転換
さて、ここまでケチャップの話をしてきましたが、まだトマトは一度も登場していません。不思議ですよね?
実は19世紀初頭まで、欧米ではトマトは「毒があるのでは」と敬遠されてきました。南米原産のナス科植物ということで、ジャガイモの芽のような危険性が疑われていたんです。
転機が訪れたのは1812年。アメリカ・フィラデルフィアのジェームズ・ミースという人物が、記録上初のトマトケチャップレシピを発表した事からでした。
ただし、当時のトマトケチャップは、今のものとはかなり違っていました。サラサラで酸味が強く、砂糖も少ない”トマト酢ソース”といった感じです。
しかも保存料も安定しておらず、すぐに傷んでしまうこともしばしば。
「開けたら急いで使い切らないと危険」という、なかなかワイルドな調味料だったわけです。
初期のトマトケチャップは”ロシアンルーレット調味料”だったかもしれません-蓋を開けるまで腐っているか分からないという、ちょっとスリリングな存在だったんですね。
それでもトマトの鮮やかな赤色と、独特の酸味は人々を魅了しました。徐々にトマトケチャップは、他のケチャップを駆逐していくことになります。
第4章:ハインツの登場と”赤い甘いケチャップ”の完成
トマトケチャップを「世界標準」に押し上げたのが、1876年にハインツが発売した製品です。
創業者のヘンリー・J・ハインツは、トマトの熟度、酢、砂糖、スパイスのバランスを徹底的に研究しました。そして、粘度と味わいが安定した、今日のケチャップの原型を確立したのです。
当時のアメリカでは、食品の安全性が大きな社会問題になっていました。不衛生な工場で作られた食品や、危険な保存料を使った製品が横行していたんです。
ハインツはこの問題に真正面から取り組みました。保存料に頼らない清潔な製造プロセスを確立し、透明なガラス瓶で「中身を見せる」という革新的な戦略をとったのです。「何も隠すものはありません」というメッセージが、消費者の信頼を勝ち取りました。
こうして「ケチャップ=甘酸っぱい赤いトマトソース」というイメージが、世界中に定着していく事となりました。
ただし、ハインツのガラス瓶には一つ問題がありました。あの独特な形状のせいで、ケチャップがなかなか出てこないんです。瓶の底を叩いたり、振ったり、ナイフを突っ込んだり—皆さんも経験があるのでは?
500年かけて海を渡ったソースは、最後は瓶の口で渋滞する運命だったというオチ…なんだか皮肉ですよね。

HEINZ(ハインツ)トマトケチャップ 1070g 1個 Amazon おすすめ
第5章:言葉の旅 ― 「kê-chiap」から「ketchup」へ
さて、ケチャップという「モノ」の旅と並行して、「言葉」も面白い旅をしています。
福建語の「kê-chiap(鮭汁)」は、魚醤を指す言葉でした。これがマレー語やインドネシア語に入り込み、「kecap(ケチャップ、キチャップ)」という形になります。
17世紀、東南アジアに進出したイギリス人がこの言葉を借用し、「catchup」「ketchup」などの表記で英語に取り込みました。
1690年の英語辞書には、早くも「高級な東インドのソース」として「catchup」が登場しています。
興味深いのは、現在の東南アジアでは「kecap」「kicap」が醤油系ソース全般を指す言葉になっていることです。インドネシアの「kecap manis(甘い醤油)」、マレーシアの「kicap」—これらは全て「ケチャップ」の親戚なんです。
語源には他の説もあります。例えば「トマトジュース」を指す中国語から来たという説など。ただし歴史研究では、魚醤ルーツ説が最も有力とされています。
考えてみれば不思議な話です。旅するうちに”魚醤ソース”の名前が”トマトソース”の代名詞になるなんて、言葉もかなりの大冒険家ですよね。
まるで「タイから来た人がフランスで暮らしているうちに、いつの間にかドイツ人と呼ばれるようになった」ような感じです。
第6章:現代のケチャップと”魚”の名残を探してみる
現代のトマトケチャップには、もちろん魚は使われていません。でも、よく考えてみてください。
「うま味を濃縮した液体調味料」というコンセプトは、元祖の魚醤とまったく同じなんです。形を変えても、DNAは受け継がれている—そう考えると、なんだかロマンを感じませんか?
実は世界には今も、魚醤ベースの”ケチャップの親戚”のような調味料が残っています。東南アジアの魚醤はもちろん、イギリスでは今でもマッシュルームケチャップが商品として販売されています。高級食材店に行けば、クルミやアンチョビのケチャップも見つかるかもしれません。
ここで一つ、想像してみてください。
もし最初に出会ったのが「魚臭いケチャップ」だったら、あなたはポテトフライにかけたいと思ったでしょうか?
おそらく答えは「ノー」でしょう。私たちは幸運にも、500年の進化の末に完成した「トマトケチャップ」という形で、この調味料と出会うことができたのです。
まとめ:ケチャップを見る目が変わる一言オチ
ケチャップの歴史を振り返ると、こんな3段階の進化が見えてきます。
魚醤(中国・東南アジア)→ きのこ&ナッツ系ソース(ヨーロッパ)→ トマトケチャップ(アメリカ)

500年以上かけて、魚臭い茶色の液体は、甘酸っぱい赤いソースへと変身しました。でも「濃厚なうま味を提供する」という役割は、最初から最後まで変わっていません。
次にポテトフライにケチャップをかけるとき、ちょっと思い出してみてください。
「これは元・魚醤エリートの末裔なんだな」と。…
あの赤いソースが、ほんの少しだけ特別に見えてくるかもしれませんよ。
ブランド: 北のうまいもん屋 4.7 5つ星のうち4.7 (43) ふらの とまとのケチャップ 290g×3本入り トマトケチャップ
追記
「今でもイギリスの一部では『Mushroom Ketchup』がソースとして売られています。また、フィリピンではトマトの代わりにバナナを使った『バナナケチャップ』が主流。ケチャップの旅は、実はまだ終わっていないのかもしれません。」
終わり
最後までお付き合い下さり有難う御座います。
この記事があなたの明日のスパイスとなれば嬉しいです。