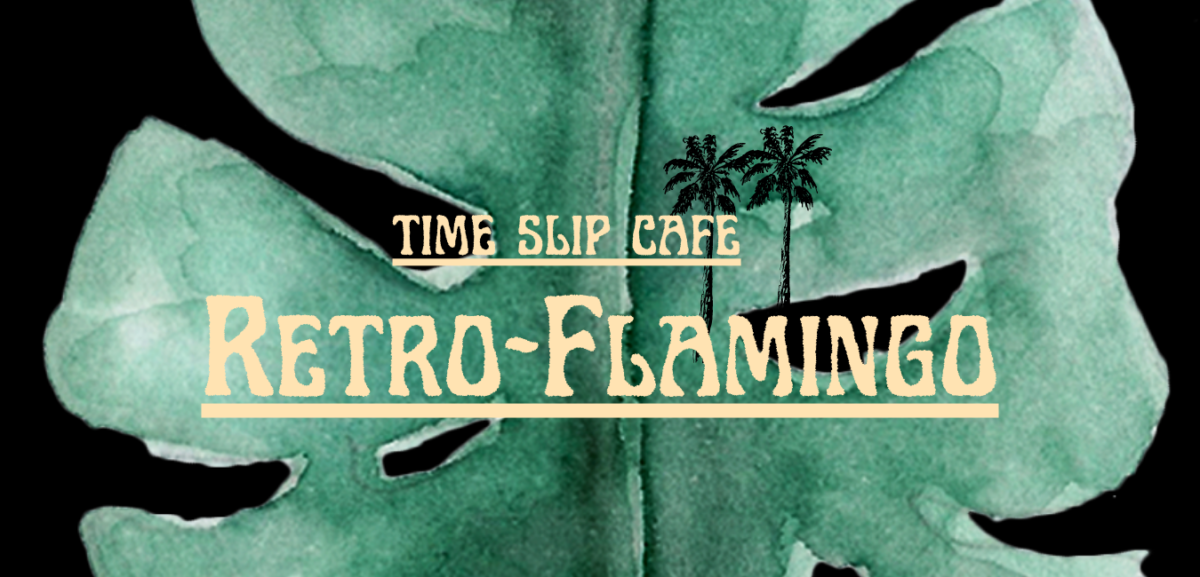もしタイムスリップして中世ヨーロッパの街を歩いたら、あなたは奇妙な光景を目にするでしょう。市場で砂糖を探しても、八百屋にも食料品店にもありません。砂糖があるのは、薬草や香辛料が並ぶ「薬局」の棚です。店主は砂糖を慎重に量り売りし、医師の処方箋を持った裕福な患者が、高価な薬として買い求めていきます。
信じられないかもしれませんが、19世紀頃まで、砂糖は「薬」として扱われていました。今では誰もが手軽に買える砂糖が、かつては王侯貴族だけが口にできる高級医薬品だったのです。この「白い結晶」をめぐる人間の欲望と壮大な勘違いが、世界の食文化を根底から変えていきました。

第1章
古代インドから始まった「甘い万能薬」の誕生
砂糖の物語は、紀元前のインドから始まります。サトウキビの搾汁を煮詰めて結晶化する技術が確立されると、砂糖は即座に医療の世界に取り込まれました。古代インドのアーユルヴェーダ医学では、砂糖は単なる甘味料ではなく、れっきとした「薬剤」として分類されていたのです。
この認識は、イスラム世界を経由してヨーロッパへと広がります。中世のアラビア語医学書には、砂糖を使った様々な治療法が記されていました。興味深いのは、イスラム世界でも長い間、砂糖は主に薬用として使われ、日常的な甘味料としての使用は祭礼や特別な宴席に限られていたという事実です。「甘さ」は、それほど特別で神聖なものだったのです。
中世ヨーロッパの医師たちは、アラビア医学を熱心に学び、砂糖の「驚くべき効能」を信じるようになります。当時の医学理論では、砂糖は体を温める性質を持ち、「冷え」や肺の不調、消化不良に効くとされました。さらに、苦い薬草の味を隠す「コーティング材」としても重宝され、砂糖シロップや糖衣錠の原型のようなものが作られていました。
ここで驚くべき事実:中世の医師たちが砂糖を推奨した理由の一つは、「高価だから効くはずだ」という論理でした。当時、薬の価値はしばしば価格と結びつけられていたのです。金や真珠の粉を薬に混ぜることもあった時代ですから、高価な砂糖もまた「貴重だから効く」と信じられたのです。
第2章
ヨーロッパ貴族が熱狂した「砂糖医療」の実態
12世紀から16世紀にかけて、ヨーロッパの上流階級では砂糖を使った医療が大流行します。医師たちは「砂糖入りの療養飲料」や「砂糖シロップ」を次々と処方し、患者たちは高額な治療費を支払ってこれらを求めました。
しかし、ここで人間の欲望が顔を出します。「薬だから体に良い」という大義名分のもと、上流階級の食卓では砂糖を山盛りにした豪華なデザート宴会(シュガー・バンケット)が開かれるようになったのです。医療と贅沢の境界線は、急速にあいまいになっていきました。
想像してみてください──重厚な宮殿の広間で、砂糖で作られた彫刻や精巧な細工菓子が並べられ、貴族たちが「これは健康のためだ」と言い訳しながら、競うように甘いものを口にする光景を。現代の私たちが「体に良いから」とサプリメントを過剰摂取するのと、本質的には同じかもしれません。
見逃せないポイント:16世紀のイギリス女王エリザベス1世は、砂糖を大量に摂取したことで知られています。彼女の歯が真っ黒になっていたという記録が残っており、これは砂糖による虫歯が原因でした。しかし当時、黒い歯はむしろ「砂糖を買える富の象徴」として、上流階級の間で羨望の対象だったのです。

第3章
遥か東の島国・日本にも届いた「薬としての砂糖」
日本への砂糖伝来は、8世紀頃、遣唐使によって中国から持ち込まれたのが最初とされています。しかし、その価格は想像を絶するものでした。輸入に頼る超高級品だったため、主な用途は「薬」と「仏前への供え物」に限られていたのです。
奈良・平安時代の日本人にとって、砂糖は文字通り「異世界の甘さ」でした。それまでの甘味といえば、蜂蜜や甘葛(あまづら:山ぶどう系の樹液を煮詰めたもの)でしたから、純度の高い砂糖の結晶がもたらす甘さは、まさに次元の違う体験だったでしょう。
宮中や貴族の間では、砂糖は漢方薬の一部として、あるいは「滋養強壮」の妙薬として扱われました。病人や虚弱体質の人に与える、現代でいう栄養剤のような位置づけです。一般庶民は一生口にすることのない人も多く、「砂糖」という言葉さえ知らない人がほとんどでした。
驚きの事実:室町時代の文献には、将軍家が重病の際に「砂糖湯」を服用したという記録が残っています。砂糖をお湯に溶かしただけのものですが、これが最高級の医療だったのです。現代の感覚では信じがたいことですが、当時の人々にとって砂糖は命を救う可能性のある貴重な薬だったのです。
第4章
南蛮貿易が起こした革命──「薬」から「お菓子」への大転換
日本の砂糖史が劇的に変わるのは、16世紀の南蛮貿易からです。ポルトガル人やスペイン人が持ち込んだのは、砂糖そのものだけでなく、イスラム世界経由で発展した砂糖菓子の製法でした。
カステラ、コンペイトウ、ボーロ、有平糖──これらの南蛮菓子は、戦国武将たちを魅了しました。織田信長がイエズス会宣教師から金平糖を献上された時の驚きと喜びは、宣教師の報告書に詳しく記されています。これらの菓子は、キリスト教布教の重要な「武器」でもあったのです。
江戸時代に入ると、砂糖の輸入量は徐々に増加し、上流階級の茶会では砂糖を使った和菓子がステータスシンボルになっていきます。練り切り、羊羹、最中──日本独自の繊細な和菓子文化が花開くのは、この時期です。
しかし、ここで注目すべきは、江戸時代の砂糖がまだ「両義的」な存在だったことです。武士や豪商は茶会で和菓子の甘さを楽しみながらも、それを「教養」や「財力」のアピールとして位置づけていました。一方、庶民にとっては依然として高価で、「薬屋で少しだけ買って、病人のためにとっておく」「お祝いの日だけ砂糖入りの料理を作る」といった、ご褒美兼お守り的な使い方が主流でした。
知られざるエピソード:江戸時代の医学書『和漢三才図会』(1712年)には、砂糖について「性は平、味は甘く、毒はなし。肺を潤し、中を和らげ、痰を消し、酒毒を解く」と記されています。つまり、お菓子として楽しまれるようになった後も、砂糖の「薬効」への信仰は続いていたのです。

第5章
大量生産が生んだ悲劇──「甘い薬」から「甘い毒」へ
18世紀、砂糖の歴史は大きな転換点を迎えます。カリブ海や南米のプランテーションで砂糖の大量生産が始まったのです。しかし、その背後には人類史上最も暗い一章がありました──奴隷制です。
数百万人のアフリカ人が奴隷として連れて来られ、過酷な労働を強いられました。「白い金」と呼ばれた砂糖は、文字通り人間の血と涙で作られていたのです。皮肉なことに、ヨーロッパの人々が「健康のため」と信じて口にしていた砂糖は、植民地では無数の命を奪っていました。
大量生産により、19世紀には砂糖の価格が急激に下がります。かつて王侯貴族だけのものだった砂糖は、労働者階級の食卓にも並ぶようになりました。イギリスでは紅茶に砂糖を入れる習慣が広まり、砂糖は完全に「日常品」となったのです。
そして20世紀に入ると、科学の進歩が砂糖の真実を明らかにしていきます。虫歯、肥満、糖尿病、心臓病──砂糖の過剰摂取と様々な健康問題との関連が次々と指摘され始めたのです。
衝撃の転換:1942年、アメリカ医学会は「砂糖摂取を制限することは公衆衛生のために望ましい」という勧告を出しました。かつて医師が処方していた「薬」が、今度は医師が制限を呼びかける「害」になったのです。現代では、砂糖は「最も邪悪な分子」とまで呼ばれ、健康系メディアでは悪役の代表格として扱われています。
おわりに
砂糖という鏡に映る人間の姿
砂糖の歴史を振り返ると、一つの明確なパターンが見えてきます。
最初は「崇高な薬」として崇められ、次に「富と権力の象徴」となり、やがて「庶民の楽しみ」に変わり、最後には「健康を脅かす悪役」として非難される──この変遷は、砂糖そのものの性質が変わったからではありません。人間の側が、砂糖に対する認識と欲望を変え続けてきたのです。
中世の医師たちが砂糖の効能を過信したのも、江戸時代の将軍が砂糖湯を妙薬と信じたのも、現代の私たちが砂糖を「毒」として避けようとするのも、本質的には同じです。私たちは常に、「甘さ」に何か特別な意味を見出そうとしてきました。
興味深いのは、砂糖に対する態度の変化が、その時代の社会構造を映し出していることです。砂糖が薬だった時代は、医療が特権階級のものだった時代。砂糖が贅沢品だった時代は、貧富の格差が極端だった時代。砂糖が悪者になった現代は、過剰消費と健康への執着が並存する時代です。
最後に考えるべきこと:私たちは今、砂糖を「控えるべきもの」として扱っていますが、100年後の人々は私たちの態度をどう見るでしょうか?「21世紀の人々は砂糖を敵視しすぎていた」と笑うかもしれません。あるいは「もっと早く気づくべきだった」と言うかもしれません。
砂糖の歴史が教えてくれるのは、人間は常に確信を持って間違えるということです。そして、その確信こそが歴史を動かしてきたのです。
次にあなたがコーヒーに砂糖を入れる時、あるいは意識的に砂糖を避ける時、思い出してください。この小さな白い結晶をめぐって、かつて医師が処方箋を書き、王が財宝のように保管し、奴隷が命を落とし、そして現代人が罪悪感を抱いていることを。
甘さの裏側には、いつも人間の欲望と勘違いの歴史が隠れているのです。