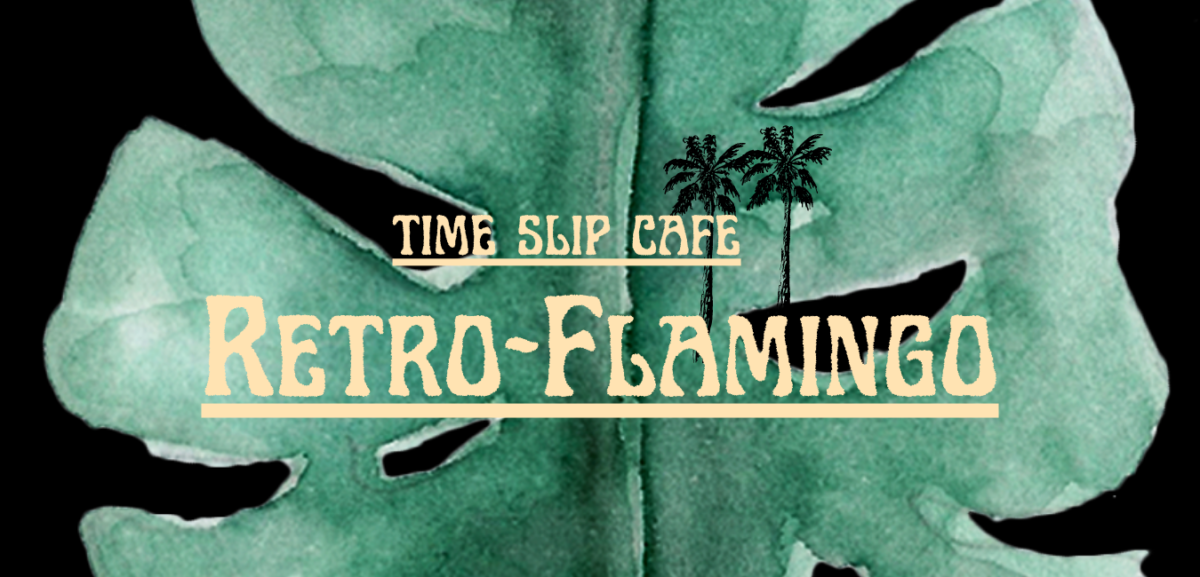—–
Boston Molasses Disaster / 発生日:1919年1月15日 / 死者21名・負傷者150名以上
—–
あなたは今、1919年1月15日のボストンにいる。
マサチューセッツ州、ノースエンド地区。移民たちが肩を寄せ合って暮らす、活気ある下町。波止場の近くでは荷役作業が続き、子供たちの笑い声が路地に響いていた。冬のボストンにしては異様なほど気温が高く、どこか気だるい空気が漂っていた。
正午を少し過ぎた頃のことだ。
突然、地底から響くような低い轟音が街全体を揺さぶった。鋼鉄が引き裂かれる甲高い金切り声。そして次の瞬間、誰もが生涯忘れられないものを目にした。
「波だ。」
だがそれは、海からやって来た波ではなかった。
黒く、ぬめりと輝き、信じられないほど粘り気のある液体の壁が、街に向かって迫ってきた。甘い、胸が悪くなるほど甘い匂いを漂わせながら。
—–
街が「甘く」崩れた日
洪水と言えば、私たちは透明な水を思い浮かべる。濁った泥水を思い浮かべる人もいるだろう。しかし、もしそれが黒くて粘り気のある甘い液体だったとしたら?
それが、ボストンの人々が直面した現実だった。
波の高さは最大約7〜8メートル。時速にして約56キロメートル。大人が全力疾走しても、とても逃げ切れる速度ではない。「甘い津波」は建物をなぎ倒し、高架鉄道の鉄骨支柱を飴細工のように折り曲げながら、ノースエンドの街を丸ごと飲み込んでいった。
その正体は——糖蜜だった。
英語でMolasses(モラセス)と呼ばれるこの黒い液体は、砂糖の精製過程で生まれる副産物だ。アルコール発酵の原料として重宝されており、すぐ近くにあったUnited States Industrial Alcohol Company(USIA)のタンクに大量に貯蔵されていた。
そのタンクが、鋼板が裂けるように崩壊した。
高さ約15メートル、直径約27メートルという巨大な鋼鉄製タンクから解き放たれた糖蜜は、約870万リットル。オリンピックサイズのプール約3.5杯分が、一瞬のうちに街へ流れ込んだ。
—–

なぜ、糖蜜は「凶器」になったのか
糖蜜なら粘りつくだけで、水よりましではないか——そう思う人もいるかもしれない。だが現実は逆だった。
粘度が高いということは、巻き込まれた人間が自力で脱出できないということを意味する。手足を動かすたびに更に深みへとはまり込む。溺れているのに、水のように流れに乗ることもできない。パニックになればなるほど、体は糖蜜の中に沈んでいく。
さらに最悪の条件が重なっていた。冬のボストンだ。
気温が急上昇したとはいえ、冬の冷気の中で糖蜜はみるみる冷えて粘度を増し、やがてほとんど固化していった。救助に向かった消防士や警察官も、膝まで黒い液体に沈みながら身動きが取れなくなった。馬が窒息して絶命した。子供が飲み込まれた。波の衝撃それ自体も凄まじく、周囲の建物は次々と押しつぶされた。
21名が命を落とした。150名以上が重軽傷を負った。
甘い匂いが、街を覆い尽くしていた。
—–
本当の問いは、「なぜタンクは破裂したのか」ではない
現場の惨状が明らかになるにつれ、人々の問いはひとつに収斂していった。
なぜ、あんなタンクが街のど真ん中に存在していたのか。
所有企業USIAは、第一次世界大戦の軍需に伴うアルコール需要の急増を受け、1915年にこのタンクを建設した。だが後に明らかになる設計の実態は、驚くほど杜撰なものだった。
設計を主導したのは、構造工学の専門家ではなかった。完成直後から各所で糖蜜が漏れており、周辺住民は異臭に気づいていたという証言が残っている。会社側は漏れを補修するのではなく、タンクを糖蜜と同じ茶色に塗装することで目立たないようにしたとの証言もある。
破裂の直接原因については、今日まで複数の説が並立している。発酵によって内部に二酸化炭素が蓄積し、圧力が限界を超えたという説。当日の急激な気温上昇が糖蜜を膨張させたという説。金属疲労と構造的欠陥が重なったという説。いずれにせよ、研究者たちが一致して指摘するのは、タンクの設計段階から深刻な問題があったという点だ。
圧力計算は不十分だった。建設時に行われるべき基本的な水圧試験の記録は残っていない。完成後に何度かタンクが揺れたり音を立てたりしていたにもかかわらず、会社は操業を続けた。
これは事故だったのか。それとも、防ぎ得た人災だったのか。
—–
裁判が暴いたもの
事件後、被害者遺族や負傷者、近隣住民ら数百人がUSIAを相手取った訴訟を起こした。
裁判は3年以上にわたって続いた。企業側は当初、「爆弾を仕掛けたアナキストによる破壊工作だ」と主張した——当時は政治的過激派への社会的不安が高まっていた時代であり、この主張は一定の「世論効果」を狙ったものだったのかもしれない。しかし専門家による詳細な検証がその主張を完全に否定し、1925年、企業は和解に応じた。支払われた賠償金は当時の価格で約100万ドル近くに上った。
これはアメリカ法史において、企業の過失による大規模災害の責任が司法で問われた先駆的事例のひとつとして記録されている。この事件を機に、ボストンをはじめとする各都市で工業施設の建設基準や安全管理規制が見直され、強化されることになった。
甘い液体が奪った21の命は、未来の無数の命を守るための礎となった——と言えば聞こえはいい。だが裏を返せば、それだけ多くの命が失われなければ、企業は「設計を見直す」程度のことすらしなかったのだ。
—–

残った「甘い匂い」の伝説
糖蜜は洗い流され、街は再建された。
現在、事件が起きた場所はLangone Park(ランゴーン・パーク)周辺として整備されており、公園や球場が広がる。かつてそこに鋼鉄のタンクが屹立し、870万リットルの黒い波が押し寄せたとは、今の景色からは想像もつかない。
だが地元のボストン市民の間には、今も語り継がれる話がある。
「夏の暑い日には、あの辺りから甘い匂いがする」——と。
科学的に考えれば、糖蜜が地中に残留するとしても100年以上が経過した今、揮発性有機物としての匂いは残りえないだろう。気象条件や周辺環境が「甘い匂い」を生み出す可能性も否定はできないが、確かな根拠があるわけでもない。
では、これは単なる都市伝説なのか。
心理学者は「嗅覚記憶」の特異性を指摘する。人間の記憶の中で、匂いに紐づいた記憶はとりわけ鮮烈で消えにくい。集合的な記憶、語り継がれた歴史が「匂いの記憶」として世代を超えて伝承される——そんなことが人間という生き物には起きうるのだ。
あるいはこう解釈することもできる。街が忘れさせてくれない、と。建物が変わり、世代が入れ替わり、それでも記憶が匂いという形をとって現れる。それは、忘却への抵抗なのかもしれない。
事実と伝説の境界線上で、「甘い匂い」はゆらゆらと漂い続けている。
—–
この事件が、現代に突きつけるもの
ここまで読んで「100年以上前の珍しい事故」として胸にしまいかけているなら、少しだけ待ってほしい。
産業革命以降、世界は「もっと大きく、もっと速く、もっと多く」を繰り返してきた。需要が生まれれば設備が作られ、設備が作られれば稼働が優先され、安全への配慮はコストとして後回しにされてきた。1919年のボストンで起きたことは、その縮図に過ぎない。
化学プラントの爆発、ダムの決壊、老朽化したインフラの崩壊——現代にも同じ構図の事故は繰り返されている。そのたびに「想定外だった」「設計上は問題がなかった」という言葉が企業から発せられる。
USIAもそう言った。アナキストのせいにすら、した。
> 危険は爆弾の形をしているとは限らない。
> ときにそれは、甘くて粘つく。
糖蜜の波は分かりやすい比喩だ。問題が表面化した時には既に手遅れで、どんなに足掻いても抜け出せない——そういう「危機」が、今この瞬間も世界のどこかの鋼鉄タンクの中で圧力を高めているかもしれない。
そして恐ろしいのは、そのタンクが「糖蜜色に塗装されている」可能性だ。
—–
エンディング:甘い匂いの正体
最後に問いを置いておこう。
もしあなたが夏の日にボストンのノースエンドを訪れ、ふと甘い匂いを感じたとしたら——それは本当に糖蜜の残り香なのだろうか。それとも、人間が何度も何度も繰り返してきた「見て見ぬふり」への警告なのか。
1919年1月15日、午後12時40分頃、ボストンの空気は甘く染まった。
その匂いは今日まで、消えていない——少なくとも、私たちの記憶の中では。
—–
Ꭲhe end
最後までお付き合い下さり有難う御座います、この記事があなたの明日のスパイスとなれば幸いです。
※本記事は当時の新聞報道、州公文書、Jonathan Harr著『Dark Tide』など複数資料を照合して構成しています。
*参考:Boston Post(1919年当時の報道)、Massachusetts Archives、Jonathan Harr著 “Dark Tide: The Great Boston Molasses Flood of 1919”(2003)など*