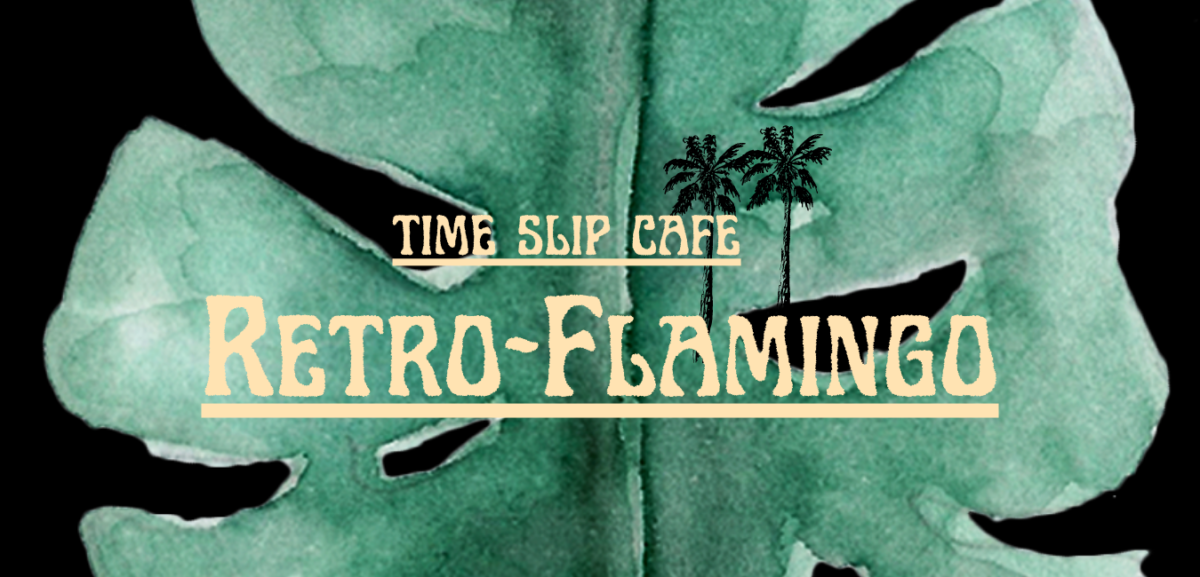「ピンクは女の子の色、ブルーは男の子の色」
私たちの多くが当たり前のように受け入れているこの常識。しかし、この色の組み合わせが定着したのは、実はここ数十年のことに過ぎません。それどころか、100年ほど前には全く逆の考え方が一般的だったのです。
1884年、後にアメリカ大統領となるフランクリン・D・ルーズベルトの幼少期の写真があります。そこに写る2歳の男児は、ドレスとスカートを身につけています。現代の私たちから見れば驚くべき光景ですが、当時これは全く普通のことでした。
では、この「常識」はいつ、なぜ生まれたのでしょうか?
その答えは、想像以上に複雑で興味深い歴史の中にあります。
白いドレスの時代 ― 性別に関係なく同じ服を着ていた子どもたち
19世紀以前、赤ちゃんや幼児の服装に性別による区別はほとんどありませんでした。18世紀から19世紀初頭にかけて、すべての赤ちゃんは白い服を着用していました。
これには実用的な理由がありました。汚れやすい赤ちゃんの服は頻繁に洗濯する必要がありますが、当時の技術では漂白剤で汚れを落とせる白い綿の服が最も実用的だったのです。色物の服は色落ちや変色のリスクがあり、赤ちゃん服には不向きでした。
さらに驚くべきことに、男の子も女の子も区別なく6〜7歳までドレスを着用していました。ビクトリア朝時代には「ブリーチング」と呼ばれる儀式があり、男児が初めてズボンを履くことは一種の成人式のような意味を持っていました。
色による性別の区別が始まったのは、19世紀半ば以降のことです。しかし、その色の割り当ては現代とは異なっていました。
「ピンクは男の子、ブルーは女の子」― 1918年の衝撃的な記録
1918年、アメリカの業界誌『Infants Department』は、当時の色の常識についてこう記録しています。
「一般的に受け入れられているルールは、男の子にはピンク、女の子にはブルーです」
現代の私たちからすれば驚くべき記述ですが、当時はこれが「常識」だったのです。では、なぜそのような色の割り当てだったのでしょうか?
その理由は、各色が持つとされた象徴的な意味にありました。ピンクは赤に近い色として「決定的で強い色」と考えられ、男の子により適しているとされました。赤は「情熱・力強さ・活動的」の象徴だったからです。
一方、ブルーは「繊細で可憐な色」とされ、女の子により美しい色と考えられていました。青は聖母マリアを象徴する色でもあり、女性的な美徳と結びついていたのです。
1927年には『Time』誌が全米の主要百貨店を対象に調査を行いました。ボストンのFilene’s、ニューヨークのBest & Company、シカゴのMarshall Fieldsなどの有名店が「男の子にはピンク」を推奨していました。ただし、他の4店舗は正反対の推奨をしており、当時はまだ統一された基準がなかったことがわかります。
色彩研究の専門家であるPantone Color InstituteのエグゼクティブディレクターLeatrice Eisemanは、「この時代、色の意味は地域や店舗、さらには個々の家庭によっても異なっていました」と説明しています。
いつ、どのように逆転したのか? ― 色の意味が変わった転換期
では、いつ現代のような「ピンクは女の子、ブルーは男の子」という常識が生まれたのでしょうか? この問いに対する答えは、研究者の間でも議論が分かれています。
1940年代の変化
第二次世界大戦後、徐々に「ピンクは女の子、ブルーは男の子」という考え方が広まり始めました。この変化には、メーカーと小売業者の戦略的マーケティングが大きく影響していたと考えられています。
学術的な議論
メリーランド大学の歴史学教授Jo B. Paoletti氏は、40年以上にわたってジェンダーと服装の関係を研究してきました。彼女の2012年の著書『Pink and Blue: Telling the Boys From the Girls in America』では、19世紀末から20世紀初頭にかけての時代は「一貫性のなさ」が特徴だったと指摘しています。完全な色の逆転があったわけではなく、地域や媒体によってバラバラだったというのです。
一方、ニューメキシコ大学の心理学者Marco Del Giudice博士は、2012年から2017年にかけて500万冊以上の書籍データベースを分析し、異なる結論に達しました。彼の研究によれば、歴史的な文献の大多数は「青は男の子、ピンクは女の子」という記述をしており、逆転の証拠はほとんど見つからなかったといいます。
ただし、新聞や雑誌などのメディアでは逆転の記録も34対28とほぼ拮抗しており、Del Giudice博士は「完全な逆転ではなく、不一致の時代があった」と結論づけています。
つまり、真実は「ある時点で劇的に逆転した」というよりも、「20世紀前半は一貫性がなく、徐々に現在の形に収束していった」ということのようです。
ベビーブーム世代が固めた「ピンク&ブルー」の常識
1940年代から1960年代にかけて、アメリカではベビーブーム世代(1946-1964年生まれ)が誕生しました。この時期、性別による服装の区別は非常に厳格化されました。男の子は父親と同じような服装をし、女の子は母親と同じような服装をすることが強く期待されました。女の子は学校でもドレスの着用が義務付けられることが一般的でした。
ユニセックスの時代
しかし、1960年代後半から1970年代にかけて、状況は再び変化します。ウーマンリブ運動の影響を受け、性別による服装の違いに疑問が投げかけられるようになったのです。
ジョンズ・ホプキンス大学のジョン・マネー博士は「ジェンダーは社会的・環境的に学習される」という研究を発表し、多くの親たちが子どもの服装に性別による差をつけることに慎重になりました。
「男の子のような服装をすれば、女の子も活動的になれる」という考え方が広まり、性別に関係ないユニセックスな子ども服が流行しました。1970年代には、Sears社のカタログに2年間、ピンクの幼児服が一切掲載されなかったという記録もあります。
1985年以降:性別区分の再強化
しかし、1980年代半ばから状況は再び変わり始めます。Paoletti教授は、その転換点としていくつかの要因を挙げています。
最も大きな影響を与えたのは、出生前診断、特に超音波検査の普及でした。出産前に赤ちゃんの性別がわかるようになったことで、性別に特化した商品を購入する文化が生まれたのです。
また、企業側のマーケティング戦略も重要な役割を果たしました。「個別化すればするほど商品が売れる」という発見は、子ども用品業界を大きく変えました。第一子が女の子で第二子が男の子なら、すべての製品を買い替える必要が生まれます。ピンクのベビーカー、チャイルドシート、おもちゃなど、高額商品にまで性別による色分けが拡大していきました。
興味深いのは、この変化を受け入れた世代の背景です。1980年代に親となった人々の多くは、第二波フェミニストの娘世代でした。彼女たちは幼少期にピンクやフリル、バービー人形を禁じられて育ったことへの反動から、「ジェンダー平等は女性らしさの否定ではない」という新しい視点を持っていました。フェミニストであっても「ピンクを着る女性外科医」を肯定する価値観が生まれたのです。
Z世代が変える未来 ― ジェンダーニュートラルの再来

2010年代後半から現在にかけて、私たちは再び大きな変化の時代を迎えています。
Z世代(1997-2012年生まれ)の価値観は、前の世代とは明確に異なります。Pew Research Centerの調査によれば、Z世代の51%が「性別は男性と女性の2つ以上ある」と回答しており、これはミレニアル世代の35%と比べて大幅に高い数値です。
ファッション業界もこの変化に対応しています。ノードストロームやサックス・フィフス・アベニューなどの高級百貨店は、ジェンダーニュートラルセクションを導入し始めました。
ファッション工科大学(FIT)のShawn Grain Carter教授は、「ファッションは世代の文化と政治信念を映し出す鏡です。Z世代は性別の二元論からの脱却を求めており、ファッション業界はそれに応えています」と説明しています。
興味深いのは、子どもの色の認識に関する研究です。子どもは2歳頃から性別の概念を認識し始め、2歳半には「女の子はピンク」という先入観を獲得します。男の子は特にピンクを避けるようになります。これは生まれつきの好みではなく、広告、メディア、おもちゃ業界からの影響によって形成されるものです。
日本への輸入とその影響 ― 欧米の価値観がもたらしたもの
日本における「ピンクは女の子、ブルーは男の子」という常識も、実は戦後の欧米文化の流入とともに定着したものと考えられます。
日本は欧米ほどウーマンリブ運動の影響を受けなかったため、1980年代以前から継続してこの色分けが存在していた可能性もあります。しかし、いずれにしても「たった2〜3世代の歴史」に過ぎないのです。
現在、この色分けはトイレのマークや更衣室など、日常生活の様々な場面に深く浸透しています。しかし近年、ランドセルの色が多様化していることは、良い兆候と言えるでしょう。かつては男の子は黒、女の子は赤というのが当たり前でしたが、今では紫、緑、茶色など、様々な色のランドセルを見かけるようになりました。
私たちが学ぶべきこと ― 「当たり前」は変わり続ける
この歴史から、私たちは何を学ぶべきでしょうか?
まず明らかなのは、「ピンクは女の子、ブルーは男の子」は生物学的な真実ではなく、商業的・文化的に構築された概念だということです。わずか100年足らずの間に、色の意味は少なくとも2度大きく変化しました。
「生まれた時からある常識」は、必ずしも「人類史上ずっと続いてきた真実」ではありません。私たちが当たり前だと思っていることの多くは、実は特定の時代、特定の文化における一時的な合意に過ぎないのです。
この認識は、子どもの教育においても重要です。子どもに「性別に適した色」を押し付けることは、本当に必要なことでしょうか? 消費主義が作り出した固定観念を、無意識のうちに次世代に引き継いでいないでしょうか?
色の好みは極めて個人的なものです。ピンクが好きな男の子がいてもいいし、青が好きな女の子がいてもいい。むしろ、色の多様性を自由に試せる幼少期こそ、子どもたちは本当に好きな色を見つけられるはずです。
Jo B. Paoletti教授は、長年の研究を通じてこう述べています。「現実の個人の世界では、すべてが白黒ではないのです」
歴史を知ることで、私たちは現在の「常識」を相対化し、より柔軟な視点を持つことができます。次世代が自分らしく色を選べる社会へ。それは、決して新しい挑戦ではなく、むしろ歴史の繰り返しなのかもしれません。
色に性別はありません。あるのは、私たち一人ひとりの個性と好みだけです。この単純な真実を、私たちは歴史から学び直す必要があるのではないでしょうか。
最後までお付き合い頂きまして有難う御座います
又次の記事でお会い出来ると嬉しいです。