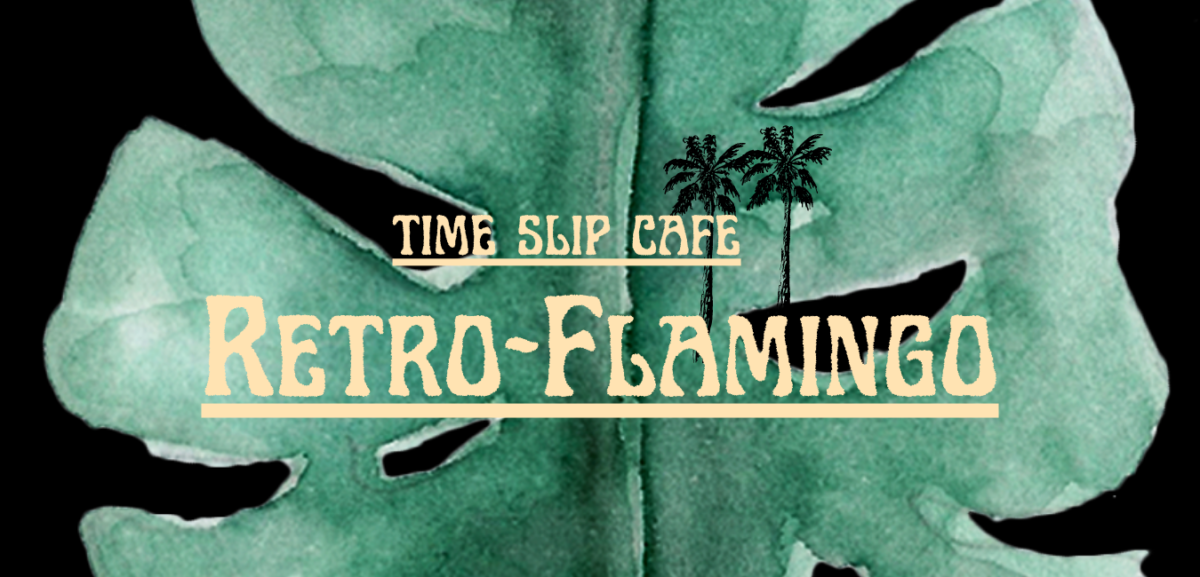スポンサーリンク

シャッターを押しても、画面には何も映らない。撮った写真をその場で確認することも、失敗した写真を削除することもできない。それでも今、Z世代は「写ルンです」を手に取る。
1986年に発売された使い捨てカメラ「写ルンです」は、累計出荷本数が17億本を超えるロングセラー商品だ。デジタルカメラの普及とともに一度は衰退したこの製品が、近年SNSを中心に再び脚光を浴びている。
「#写ルンです」「#filmcamera」といったハッシュタグの投稿は増え続け、若者たちが日常や旅行、ポートレートをフィルムで撮影する文化が広がっている…
なぜデジカメ・スマホ世代が、あえて「不便でコストもかかる」アナログを選ぶのか?…
この問いの答えには、Z世代の消費スタイルを理解する重要な鍵が隠されている。
「写ルンです」ブームの現在地 ― Z世代の使い方とシーン
若年層のフィルムカメラ人気が再燃したのは2020年代に入ってからだ。10〜20代が店頭でフィルムや使い捨てカメラを購入する光景が、再び日常的に見られるようになった。
「スマホだときれいに撮れすぎちゃって、逆に面白くないんです」
都内の大学に通う22歳の女性は、そう話す。彼女が好んで撮るのは、粒状感のある、少し「粗い」写真だ。
レトロな喫茶店、夕暮れの街角、友人との何気ない瞬間。完璧すぎない写真が、かえって「その時の空気感」を残してくれると感じている。
写ルンですが使われるシーンは多岐にわたる。旅行スナップ、日常のポートレート、街の風景、古い商店街や純喫茶など「雰囲気が出る」場所での撮影が特に人気だ。
そして何より、誕生日や卒業旅行といった人生のイベントで使われることが多い。「現像が上がるまで何が写っているか分からない」というドキドキ感が、特別な日の記憶をより強く心に刻むからだ。
Z世代が感じる「エモさ」の源泉 ― 不便さ・制限・予測不能性
写ルンです人気の核心は、すぐに画像を確認できない「アナログさ」にある。スマホなら撮った瞬間に結果が分かるが、写ルンですは現像を待たなければならない。
この一見不便な特徴が、Z世代にとっては新鮮な体験になっている。
現像を待つ時間そのものが「ワクワクするイベント」になり、日常を少しだけ非日常に変える。写真屋に現像を出してから数日後、仕上がった写真を手に取る瞬間は、まるで未来の自分からの手紙を開封するような感覚だ。
デジタルの即時性に慣れた世代にとって、この「待つ楽しみ」は逆説的に貴重な体験となっている。
1本あたりの撮影枚数が限られることも、写真の価値を高めている。27枚撮りなら27回しかシャッターを切れない。この制限が、撮影者に「1枚を大切に撮る」姿勢を生み出す。
構図を真剣に考え、撮る瞬間に集中する。無限に撮ってすぐ消せるスマホ文化とは対照的に、制限があるからこそ写真が儀式化し、体験が記憶に焼き付くのだ。
「今のデジタルはきれいに撮れすぎる」という声は、Z世代の間で珍しくない。解像度が低く、粒子感や色の揺らぎがある写真が、かえって新鮮で「エモい」と受け取られている。
フィルム特有の色味・質感は、加工アプリなしで「それっぽい」雰囲気を出せる。この「完璧すぎない美しさ」が、Z世代の審美眼とマッチしているのだ。
「エモ消費」としての写ルンです ― ノスタルジアと自己表現
写ルンですブームは、より大きな消費トレンドの一部だ。それは「エモ消費」と呼ばれる、理屈や機能よりも感情的な満足や「ときめき」を重視する消費スタイルである。
興味深いのは、Z世代の多くが写ルンですの全盛期をリアルタイムで経験していないという点だ。
彼らが惹かれているのは、実際には経験していない過去への憧れ、いわば「歴史的ノスタルジア」である。昭和レトロ・平成レトロブームと軌を一にするこの現象は、純喫茶、レトロ遊園地、古い商店街など「昭和っぽさ」が提供する「エモい時間」への渇望と深く結びついている。
同時に、写ルンですはSNS世代の「自己演出ツール」としても機能している。スマホで完結する写真体験に飽きた若者が、「他とは違う自分」「センスのある自分」を演出するために写ルンですを選ぶ。
写ルンですで撮った写真をSNSに上げる行為そのものが、Z世代にとってのステータス記号になっているのだ。
ある20歳の男子学生は言う。「みんながiPhoneで撮った写真をインスタに上げてる中で、フィルムの写真を上げると『おっ、こいつ分かってるな』って思われるんですよね」…機能的価値ではなく、象徴的価値が消費を動かしている典型的な例だ。
スマホアプリ・チェキとの連動 ― デジタルとアナログのハイブリッド文化
写ルンですブームを語る上で見逃せないのが、デジタルとアナログのハイブリッド文化だ。
2017年前後から、Huji CamやDAZZなど、フィルム風の質感を再現するスマホアプリが人気を集めた。これらのアプリで「写ルンです的表現」を先に体験した世代が、次のステップとして本物の写ルンですに移行しているという流れがある。デジタルのシミュレーションが、アナログへの入り口になっているのだ。
チェキや平成のデジカメも「エモかわ」なアイテムとしてZ世代に再評価されている。特にチェキは「推し活」やイベントで重宝され、物理的な写真が「推しとの接点」として特別な価値を持つようになった。
デジタルデータにはない手触り、物質性が、記憶と感情を強く結びつける媒体として見直されているのだ。
マーケティング的読み解き ― 「不便」がブランド資産になる時代
写ルンですブームは、マーケティングの観点から見ても示唆に富んでいる。
デジタル技術が行き着くところまで行った結果、「機能的価値」だけでは差別化しにくくなった。即時性、画質、編集の自由度といった軸では、スマホに勝てる製品はほとんど存在しない。
しかし写ルンですは、別の戦場で戦っている。「時間をかける楽しさ」「1枚の重み」「予測不能性」という体験価値において、スマホを上回る魅力を提供しているのだ。
1980年代からの歴史を持つロングセラーブランドであることも、写ルンですの強みになった。本来なら「古くてダサいモノ」として忘れ去られてもおかしくなかったが、平成レトロ・昭和レトロという文化的文脈の変化により、「エモい・センスのあるアイテム」へと転換した。
カセットテープやレトロゲーム機など、他の「古いモノ」にも同様の現象が起きている。
企業が学ぶべきポイントは明確だ。「便利さ」ではなく「感情」「物語」「体験プロセス」をどう設計するかが、Z世代向けブランドの鍵になっている。
既存プロダクトでも、「不便さ」や「アナログ感」を再解釈することで、新しい価値提案やエモ消費への接続が可能なのだ。
写ルンですは、デジタル化の波に飲み込まれるどころか、その反動として新たな存在意義を獲得した。これは「便利競争」の終点を迎えた市場において、「あえて不便」という戦略が有効であることを示す好例だ。

写ルンですが映し出す、Z世代の「時間」と「記憶」の感性
写ルンですブームは、単なるレトロブームではない。それは、Z世代が「写真」そのものよりも、その前後に流れる時間や一緒にいる人との関係を大切にしたいという感性の表れだ。
撮影する瞬間の緊張感、現像を待つ期待感、仕上がった写真を友人と見返す喜び。
写ルンですは、撮影から鑑賞まですべてのプロセスを「体験」として設計されている。この「わざわざ感」を楽しむ感性は、カメラに限らず、音楽、文具、ファッションなど、あらゆるマーケットで今後ますます重要になるだろう。
便利さの先にある豊かさとは何か。効率の対極にある価値とは何か。写ルンですを手にするZ世代は、そんな問いを私たちに投げかけているのかもしれない。
-終わり-
最後までお付き合い頂き有難う御座います!
この記事が貴方の日常のスパイスとなれば嬉しいです。
スポンサーリンク