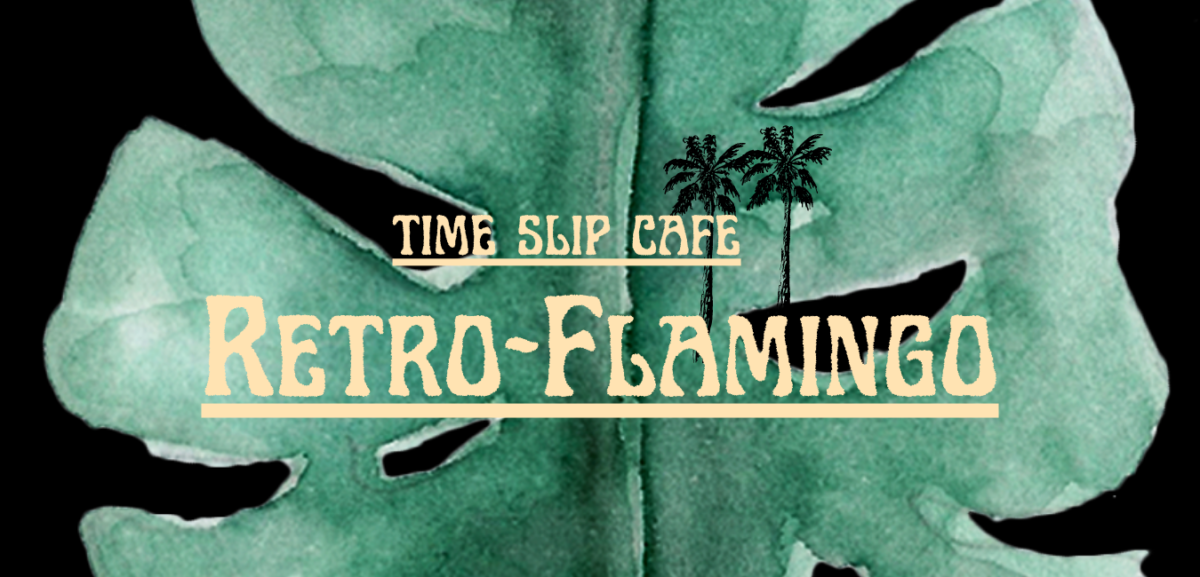スポンサーリンク

現代に生きる「2つの年齢」の違和感
履歴書を書くとき、病院で問診票に記入するとき、私たちは何の疑問もなく「満年齢」を使います。ところが、神社で七五三の受付をしたり、親戚の法事に参加したりすると、突然「数え年では何歳ですか?」と尋ねられて戸惑った経験はないでしょうか。
数え年とは、生まれた瞬間を「1歳」とし、その後は誕生日ではなく元旦(1月1日)に全員が一斉に年をとるという、不思議な年齢の数え方です。
つまり、12月31日に生まれた赤ちゃんは、翌日の元旦には「2歳」になってしまうのです。
現代の感覚からすれば、なんとも非効率的で曖昧なシステムに思えます。それなのに、なぜ厄年や七五三といった伝統行事の中では、この古い数え方が今なお頑なに守られているのでしょうか。
その答えは、日本人が大切にしてきた独特の「生命観」と「時間感覚」の中に隠されています。
数え年のルーツ:命は「誕生」ではなく「宿った瞬間」から
お腹の中の10ヶ月を認める慈しみ
西洋的な考え方では、人生は「この世に生まれ出た瞬間」から始まります。
だから「0歳」からスタートするのです。
しかし日本人は古来、もっと前から命を数えていました。それは母親のお腹に宿った瞬間です。
十月十日(とつきとおか)、母の胎内で育まれる時間。その尊い営みを「まだ生まれていないから数えない」のではなく、「すでに生きている」として敬意を持って数えに入れる。
数え年の「生まれた時が1歳」という考え方には、そんな日本人の優しい生命観が息づいているのです。
また、「0(ゼロ)」という概念が庶民に広まったのは比較的新しい時代です。それ以前の日本人にとって、物事の始まりは「1(最初)」であり、命もまた「最初の1」から数えるのが自然だったのでしょう。

「年神様」からもらうお年玉
もう一つ、数え年を理解する上で欠かせないのが「お正月」の持つ意味です。
かつての日本では、誕生日は今ほど重要な日ではありませんでした。それよりも大切だったのは元旦—年神様が各家庭を訪れ、新しい年の魂(活力)を分け与えてくれる特別な日でした。
この「年神様から授かる新しい魂」こそが、現代の「お年玉」の語源です。そう、昔のお年玉はお金ではなく、年神様の魂が宿るとされる「お餅」だったのです。鏡餅を年神様へのお供えとして飾り、それを家族で分け合って食べることで、新しい年の生命力を共有する—これが日本の正月の本質でした。
つまり、年をとるということは個人の記念日ではなく、「共同体全体で新しい季節を迎える更新の儀式」だったのです。だからこそ、みんな一斉に元旦に年をとる数え年のシステムが、当時の日本人の感覚にしっくりきたのでしょう。

歴史の転換点:明治35年、政府は「満年齢」を命じた
西洋化への反発
明治時代、急速な近代化を進める日本政府は、西洋に倣って「満年齢」の導入を試みました。明治35年(1902年)に「年齢計算ニ関スル法律」が制定され、公的には満年齢を使うことが推奨されたのです。
ところが、国民の反応は冷ややかでした。
「一人ひとりがバラバラに年をとるなんて、なんだか寂しい」
「お正月に家族みんなで年を祝う風習はどうなるのか」
農耕社会を基盤とした当時の日本では、春夏秋冬という共同体の季節感や、村全体で行う年中行事のリズムが生活の中心でした。個人の誕生日に年をとるという西洋的な時間軸は、そうした暮らしにはなじまなかったのです。
結局、法律で定められたにもかかわらず、庶民の間では数え年が使い続けられました。そして昭和25年(1950年)、ようやく「年齢のとなえ方に関する法律」が施行され、満年齢が正式に普及するまで、実に半世紀近くもの時間がかかったのです。この執念とも言える抵抗は、単なる保守性ではありません。日本人が「時間の数え方」に込めていた精神性の深さを物語っています。
なぜ「厄年」や「七五三」は数え年なのか?
先回りする先祖の知恵
現代でも数え年が使われる代表的な場面が「厄年」です。
男性の大厄は数え年で42歳、女性は33歳。この厄年を満年齢に換算すると、実際には1〜2年前倒しになります。つまり、「体に異変が起きてから対処する」のではなく、「起きる前に予防する」という先祖の知恵が込められているのです。
人生の節目で心身を律し、神仏に祈りを捧げ、生活を見直す。厄年とは、科学的根拠というよりも、人生の危うい時期を乗り越えるための「心の準備期間」だったのかもしれません。
神様との時間軸を共有する
七五三や厄払い、法要といった神事や祭礼は「ハレ(非日常)」の世界です。そこでは日常の時間ではなく、神様や仏様、ご先祖様と同じ時間の流れを共有することに意味があります。
明治以降に輸入された西洋的な時間軸ではなく、古来から続く「神々の暦」である数え年を使うことで、私たちは無意識のうちに聖なる空間へと足を踏み入れているのです。
だからこそ、神社やお寺では今も数え年が生きている。それは単なる慣習ではなく、「祈りの作法」そのものなのです。
12月31日生まれの赤ちゃんは「2歳」になる——最短記録の悲喜劇
数え年の極端な例として、よく語られるのが「大晦日の深夜に生まれた赤ちゃん」の話です。
12月31日の午後11時59分に生まれた子は、生まれた瞬間に「1歳」。そして、わずか2分後の元旦午前0時には「2歳」になってしまいます。
現代の感覚からすれば「そんなバカな!」と思わず笑ってしまいますが、この極端な例こそが、数え年の本質を物語っています。
それは、「個人の経過時間」よりも「社会全体の季節感」を重んじる、日本人の大らかな時間感覚です。一人ひとりの細かな違いよりも、みんなで同じ節目を祝い、共に年を重ねていくことの方が大切だった—そんな価値観が透けて見えてきます。

時間を「積む」のではなく「迎える」
2つの年齢が教えてくれること
満年齢は「経過した時間(過去)」をカウントします。「私は何年生きたか」という個人の履歴です。
一方、数え年は「新しく迎える年(未来)」をカウントします。「私たちは今年、何年目を生きるか」という共同体の展望です。
どちらが正しいということではありません。ただ、両方の時間軸を持つことで、私たちはより豊かに人生を捉えることができるのではないでしょうか。
先祖が見ていた景色を共有する
七五三で神社を訪れたとき、厄年にお祓いを受けるとき、あるいは亡くなった祖父母の法要で数え年を聞かれたとき—。
私たちは無意識に、先祖が見ていた景色を共有しています。
お正月にみんなで一斉に年をとる感覚。年神様を迎えて新しい魂をいただく喜び。お腹の中の命も、この世に生まれた命も、同じように尊く数える優しさ。
それは効率や論理では測れない、日本人の時間に対する感性そのものです。
忙しい現代だからこそ、誕生日に1つ増える「点」の年齢だけでなく、元旦にみんなで新しくなる「線」の時間を大切にしてみませんか?
数え年という古い数え方の中に、私たちが忘れかけていた「ゆっくりと、みんなで、共に生きる」という豊かさが、静かに息づいているのかもしれません。
-終わり-
最後までお付き合いくださり有難う御座います。
この記事があなたの明日のスパイスとなれば嬉しいです。
スポンサーリンク